著者:エドガー・H・シャイン 訳者:金井真弓
(サブタイトル:本当の協力関係をつくる7つの原則)
本当に人の役に立つにはどうしたらよいか、助けたり助けられたりするときの根本にある心の動きを具体的な例を挙げて分かり易く解説している。
会話の仕方の向上にも役に立つ、タイトルに違わず "ヘルプフル"な一冊。
チームワークについて書いてある部分で思い出したのはこの聖句。
コリント第一12:14-26(抜粋)
実際,体は一つの肢体ではなく,多くの肢体です。
たとえ足が,「わたしは手ではないから,体の一部ではない」と言ったとしても,そのためにそれが体の一部でないというわけではありません。もしそのすべてが一つの肢体であったなら,体はどこにあるのでしょうか。しかし今,それは多くの肢体であり,それでもなお一つの体です。
目は手に向かって,「わたしにあなたは必要でない」とは言えず,頭も足に向かって,「わたしにあなた方は必要でない」とは言えません。
一つの肢体が苦しめば,ほかのすべての肢体が共に苦しみ,ひとつの肢体が栄光を受ければ,ほかのすべての肢体が共に歓ぶのです。
チームには責任の重い役割があり、そうでもない役割もいることに変わりはない。
それでも、目的達成のために誰もが必要な存在であることを責任ある人が認めるなら、
チームは互いに助け合う集団として機能する。
逆に、責任ある立場の人が「お前の代わりなんかいくらでもいるんだ」という態度では、チームは本来の目的を達成しにくくなるし、意見を言うことすら難しくなってしまう。
果たす責任の違いという意味では確かに高い立場も低い立場もある。
それでも、立場にかかわらず自分の分を果たすことを心から喜ぶ人たちでできた集団、それが成功するチーム。
上の聖句を当てはめているクリスチャンが集まって会衆を構成しているところには、この「相互扶助」が機能している。
誰もが神の目的の中での自分の役割を知っていてそれを喜んで果たし、立場の違いなど気にせずに意見を交換し、互いに励ましあうことができる。 果たしている責任が小さいからといって申し訳なく思う必要はないし、助けてもらったからといってメンツがつぶれるわけでもない。
この本を読む前から、人を助けるとはどういうことかを体験して知り、いつの間にか自分も本当に人の役に立つ行いを実践している ー それが、本物のクリスチャン。
タイトル一覧に戻る
 聖書カバーのお店
White Fang
聖書カバーのお店
White Fang


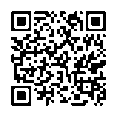
コメントをお書きください