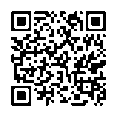著者:ローレル・ブライトマン
訳者:飯島貴子
心の病による症状から、筆者の愛犬は留守番中に自宅の窓ガラスを突き破って転落した。
愛犬の死をきっかけに筆者は心を病んだ動物たちの調査を始める。
ペット・動物園・サーカス・実験動物…
その調査の幅の広さ、綿密さ、深い論考と問題提起、現代社会とペットオーナーへの提言の適切な鋭さは称賛に価…するけど、White Fang はこの本は称賛しない。
こういう筆者を褒めてはいけないのである。

こんなことさせられたら
病気になるわな
White Fang
OCDという病気がある。不必要な行為だとわかっていてもそれを執拗に繰り返してしまい、日常生活に支障が出る。主に不安を発端とするもので、不安を解消しようとして何度も戸締りを確認したり、手が擦り切れてもそれでも何度も繰り返し手を洗ってしまう。
2019年5月の JW Broadcasting にもそんな兄弟姉妹が出ていた。
この本を褒めるということは、OCDの人に「キレイに手を洗ってえらいね!その調子で隅々まで洗って殺菌してね!」と言うようなものである。
だから褒めてはいけない。何の意味もないし、解決にならない。
むしろ余計に悪くなるかもしれない。

「私たちは何者で、どこから来て、
どこへ行くのだろう。」
「…さあな。」
White Fang
確かに愛犬の死は衝撃だったろう。
しかし、どんなに精力的に、こころの病にかかった動物の調査をしても、
そこから学んでも、学んだことを本に書いても、愛犬は還ってこないのだ。
自分がしっかりしていなかったから愛犬が死んだという罪も、
こんな立派な本が書けるほどの調査研究をしたところで濯げるわけではない。
というか、そもそもこれは濯がねばならぬような罪ではない。
愛犬が死んだ、ただそれだけのことだ。
つまり、この本の存在自体が筆者の手洗い行為なのである。
必死になって手を洗い続けた結果、この本が出来上がった。
不安と悲しみと罪悪感を必死になって濯ごうとした結果、この本が出来上がった。
ペットの死を悲しむことを否定しているのではない。
悲しいからといって自分の人生を棒に振る程何かに没頭するのはよくないということだ。
OCDでもペットロスでなくても、このパターンで自分を苦しめている人は多いと思う。
周囲の人はこういう人がネガティブなきっかけを動機にして没頭している行為や、
それによって成し遂げられた事柄を褒めてはいけない。
例えば会衆に、愛する人の死について自分に責任があると思っていて、楽園でその人の復活を出迎えて、開口一番謝罪しなければならないという思いで必死に開拓奉仕をしている人がいるとしたら、その人を「開拓を頑張っている」ということで褒めてはいけない。
ネガティブな動機で行動するパターンが強化されるだけで、そんなことを褒めても少しもその人は幸せにはなれない。
楽園も復活も、神の主権の立証についてくるおまけみたいなもので、奉仕の目的はそこにある。励ますならその視点だ。
そして幸せになるには、もっと根本的に、悲しみや不安を解消しなくてはいけない。
不安を解消するには、事実を真正面から受け入れるのが第一歩である。
ペットロスの場合の事実とは
① 動物は死ぬ。楽園になっても死ぬ。
② 動物は復活しない。

それを食べた日に
あなたは必ず死ぬ。
創世 2:17
White Fang
動物が復活しないのは、次の聖句からわかる。
ヨブ 1章2,3節
ヨブには7人の息子と3人の娘がいた。所有していた家畜は、
羊7000匹、ラクダ3000頭、牛1000頭、ロバ500頭だった。
ヨブ 42章10,12,13節
エホバは、ヨブが以前に持っていたものを、2倍にして与えた。
ヨブは、羊1万4000匹、ラクダ6000頭、牛1000対、
雌ロバ1000頭を持つようになった。
さらに、息子7人と娘3人を持つようになった。
ヨブが失った動物は2倍になっているが、子どもたちの数は元のままだ。
理由は、試練の時に死んだ子どもたちは復活するから。
復活してきたら最終的にヨブの子どもの数は2倍だ。
逆に考えれば、動物は復活しない。
動物は罪を犯さないけど、命の木の実を食べないから、楽園になっても死ぬ(創3:22)。

ペットとの関係より
たいせつなものがある
White Fang
死んだペットに関する不安を解消する他の方法は、不安に支配されている自分に、死んだペットが何か一言もし言ってくれるとしたら何と言うだろうかと考えることである。
育て方や飼い方について不平や不満を言うところが想像できるだろうか。
もっともっと手洗い行為に没頭して苦しんで罪を償えと言うだろうか。
決してそんなことはない。
窓から飛び降りて死んだ筆者の愛犬オリバーもきっとこう言うだろう。
「もう元の生活にもどって幸せになっていいんだよ」
 聖書カバーのお店
White Fang
聖書カバーのお店
White Fang