筆者:村田厚生
(サブタイトル:失敗とうまく付き合う法 )
本で読んで学んだことがすぐに使えて役に立つと嬉しいものだ。
聖書もこう勧めている。
ヘブライ5:14
使うことによって自分の知覚力を訓練(する)
人はなぜ失敗するのか、小さな失敗を大きな事故にしないためにどうしたらよいかなど、実際に役立つ「エラー」との付き合い方を分かり易く解説している。
しかも、まさにこの本を読んでいる最中に、この本で学んだことが役に立つからすごい。

失敗しちゃって
はずかしいときは
赤面するって知ってた?
White Fang
本文中でカタカナの言葉を使うとき、筆者は最後の長音記号を省く癖がある。
でも、その部分の内容を解説する図の中では長音記号がついている。
(例:エレベータ/エレベーター)
同じものを表しているのだから本文と図で表記を統一した方がいいはずなのに、どうしてこの、「本文と図で言葉遣いが違う」というエラーが発生しているのか。それがまさにこの本を読むと容易に分析できるのである。まるでワークブック。
ヒューマン・エラーの本の中に、ちゃんと(?)ヒューマン・エラーがちりばめられている。
読み終わる頃には、出版社向けの校正箇所リストとこの本に書かれていることに基づいた再発防止策のレポートが書けてしまうくらい、学んだことを即座に使って読者の知覚力は訓練されていく。

んなわけねぇだろ
…ったくもぅ
White Fang
同様に、読みながら筆者に「それはお前や!」と関西弁で突っ込みを入れたくなるのが、
「99.9%は仮説~思い込みで判断しないための考え方~」という本。
これはひどい。ひどすぎる。
どんなふうにひどいのか挙げるときりがないので一言だけ。
筆者は、自分は思い込みで判断していないと思い込んでいる。ご愁傷様。
柔軟な発想ができていない人が多いという発想は、すでに固いと思う。
タイトル一覧に戻る
 聖書カバーのお店
White Fang
聖書カバーのお店
White Fang

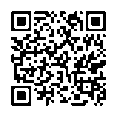
コメントをお書きください