筆者:千代島雅
エントロピーの法則について語っている項で、筆者は、
「エントロピーの法則なんて間違っている」という意味の主張をしている。
主張の裏付けとして、エントロピーの法則が働くスタート地点がおかしいといっている。
話の流れを要約すると…
例えば、一般に分かり易くエントロピーの法則を説明するとき、
氷は低エントロピー状態、水は氷よりもエントロピーが高い状態。
コップの水の中にある氷がとけていくように、物質は低エントロピー状態から高エントロピー状態に向かう…と説明される。
でも、自然な状態でコップの水の中に急に氷が出現することはありえない。
つまり、エントロピーの法則が働き始める最初の低エントロピー状態自体が自然発生しないから、自然界にエントロピーの法則が働いているとは言えない。
水の中に氷が出現するとしたら(まさか神様に登場していただくわけにはいかないので)次の三つである。
…と言って三つの可能性を挙げる。(昔から氷だった…とか)
…次に、その三つの可能性があり得ないことを説明する。(昔から氷だったのなら、観察し始めた時にタイミングよくとけはじめるなんてヘン…とか)
…だから、エントロピーの法則が働く状態が発生することが自然界ではありえないから、エントロピーの法則なんて間違っている。
とまあ、こんな感じ。

この実験のために
塔を傾けておきました
White Fang
素直なクリスチャンの立場からこれを読むと、この文章の中では、エントロピーの法則が働く状態が発生する可能性がぜんぶで4つ挙げられている。
そして、そのうちの3つだけが否定されていて、4つ目がまだ残っている。
エントロピーの法則がおかしいというよりむしろ、エントロピーの法則に4つ目の可能性がどのようにかかわっているのか検証する方が科学者が次にするべき論理的な思考の順序なのではないか。
本物の科学者なら自分の能力の低さが原因で否定できない可能性を無視してはならない。
その4つ目の可能性が正しいとすると、物質が高エントロピー状態に向かっていくならいちばん最初はなぜ低エントロピーだったのか説明できるし、エントロピーの法則が働いているなら物質はどんどん無秩序になっていくはずなのに宇宙が驚くほど規則正しい理由もわかる。
そして、エントロピーの法則を発見したとされているウィリアム・トムソン(ケルビン卿)は、次の聖書の言葉を研究したことがこの法則発見の一助になったといわれている。
詩編102:24-27
わたしは言いはじめました,
「わたしの神よ,わたしの日の半ばにわたしを取り去らないでください。
あなたの年はすべての代に及びます。
あなたは昔,この地の基を据えられました。天はあなたのみ手の業です。
それらのものは滅びうせますが,あなたご自身は立ちつづけます。
それは衣のようにみな古びてしまいます。
あなたは衣服のようにそれを取り替えられます。そしてそれは用を終えるのです。
しかしあなたは同じであり,あなたの年が全うされることはありません。」
問題は、エントロピーの法則が正しいかどうかじゃない。
すべての可能性を考慮するかどうかということだ。
タイトル一覧に戻る
 聖書カバーのお店
White Fang
聖書カバーのお店
White Fang

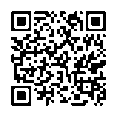
コメントをお書きください